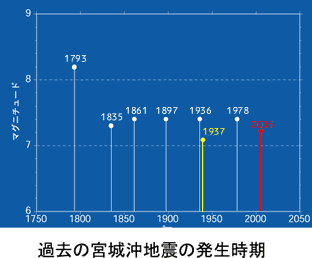1978年の宮城県沖地震(M7.4)から27年目となる今年、そろそろ次の宮城県沖地震が心配されるなかで、8月16日に宮城県沖を震源とする強い地震(M7.2)が発生し、宮城県南部で震度6弱、岩手県内陸南部、宮城県北部、福島県中通り、同浜通りで震度5強を観測したほか、北海道から四国にかけての広い地域で揺れを感じました。この地震は想定されている宮城県沖地震よりも小さいことから、1978年の再来なのか?それとも宮城県沖地震とは違うアスペリティが動いた地震なのか?が関心を集めています。
ふたつでひとつ?
宮城県沖地震の大きさと発生時期を見てみると、ばらつきはありますが、平均で37年ごとにM7.4程度の地震が発生しています。今回の地震は前回から27年目と間隔が短く、大きさもやや小さいことがわかります。
1936年の宮城県沖地震の8ヵ月後に、1936年の震源のすぐそばでM7.1の地震(黄色)が発生しています。東北大学の研究者は、この2つの地震をひとつの宮城県沖地震と考え、今回の地震(赤色)はそのうちの最初の地震で、非常に近い将来に宮城県沖で今回程度かそれより大きい地震が発生する可能性が高いと考えています。
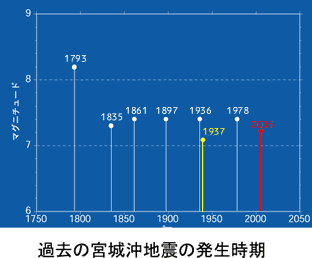
引き続き発生する可能性が高い
1936年と1937年の地震分布と1978年の地震分布を比べてみると、1936、37年の分布をあわせたものが1978年の分布とほとんど重なります。このことから、宮城県沖のアスペリティは、1936、37年の地震では、まず36年に東部のアスペリティが壊れ、その翌年37年に西部が壊れたと考えられます。このときは2度に分かれてアスペリティが壊れたために、それぞれの地震の大きさは1978年に比べてやや小さくなったと推定されます。それに対して1978年には、アスペリティは一度に壊れて大きな地震を発生させたと考えられます。
今回の本震と余震分布を1936、37年と1978年の地震と比べてみると、本震は1978年の震源とほぼ同じ位置ですが、余震分布は1936年の地震に似ています。そのため、今回も1936、37年のようにアスペリティの破壊が2回に分かれて起きる可能性があり、今後同じような規模あるいはそれより少し大きい地震が発生する可能性があります。
東北大学では、今回の地震と1936年の震源域との比較をさらに進め、今後予想されている地震活動の推定に役立てていきます。また、1933年に宮城県沖で発生したM7.1の地震を含めて解析を進め、宮城県沖地震の地震発生モデルを高度化していく予定です。
むすびにかえて
この企画展の最終準備のさなかの8月16日に宮城県沖でM7.2の地震が発生し,宮城県を中心に被害がありました.当初はこの地震が「宮城県沖地震」とも考えられましたが,その後の検討では,想定された「宮城県沖地震」ではないという見解が多数を占めているようです.また,この地震によって「宮城県沖地震」の発生が早まるのではないかとの見方もあります.
8月16日の地震の被害は,「1978年宮城県沖地震」のそれにくらべると,かなり少なかったといえます.これは,地震の規模が小さかったということに加えて,宮城県を中心とする東北地方で,地震に対する準備が,建物だけでなく私たちの心構えにおいても,ある程度そなわっていたことにもよるのかもしれません.被害の早急な復旧ももちろん重要ですが,まずは被害を出さないこと,出来るかぎり小さくすることに全力をそそぐべきでしょう.
今回の企画展が地震に関する皆様の理解や地震に対する備えを考える上で少しでもお役に立てばさいわいです.先日の地震もまた私たちにいくつかの新たな教訓を示してくれました.これらをふまえた新たな地震研究の成果についてはまたご紹介する機会があると思います.
「東北大学総合学術博物館のすべて」シリーズは,今後も第5弾,第6弾....が予定されています.総合学術博物館は,これらの企画展を通じて東北大学の研究成果を皆様に提示して行く所存です.ご期待ください.
東北大学総合学術博物館
|