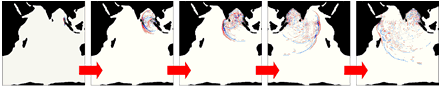・1978年宮城県沖地震の被害調査 |
||||||||||||||||
建物耐震診断の始まり 志賀敏男東北大学名誉教授は,宮城県沖地震の鉄筋コンクリート構造物の被害調査から2次壁を含む壁量と柱量と被害が比例関係にあることを見出し,現行の建物の耐震診断法の契機となりました。
この地震では,局所的には震度7という強い揺れが観測されました。また,ゆれの方向は東西方向に強いゆれが観測されています。
宮城県や仙台市では逼迫する宮城県沖地震の発生による地震被害が懸念されています。 前回の地震では,地盤の違いにより被害が違いました。そこで,実際に仙台市の地盤構造を調べ,地域での地震の揺れを推定しました。その結果は,長町ー利府活断層帯を境に,沖積地盤が厚い地域で揺れが大きく,洪積地盤で揺れが小さいことを示しています。
緊急地震速報 地震ははじめにP波による微動があり,つぎにS波による大きな揺れが来ます。そこで,大きな揺れが来る前に,緊急地震速報から設置地点での震度と大きな揺れの予想到達時刻までの残り時間を警告します。
即時対応型地震防災システム 地震被害を低減するためには,地震が起こる前に予め揺れ易く,被害の生じやすい場所を把握し,実際に地震が起きた際に,実際の揺れの強さを即時に把握し,対応することが重要です。そのために地震後直ちに揺れの強さ分布を推定するシステムの開発を進めています。 津波災害の恐ろしさ 明治29年三陸大津波は2万人以上の犠牲を出しました。近年の開発により沿岸にはさまざまな施設が置かれ,津波被害も複雑化している。北海道南西沖地震津波では,北海道奥尻島青苗地区では大規模な火災が発生し,被害を拡大しました。
防潮堤の整備 高所移転が難しい地域の場合には,居住地区を高い防潮堤で囲み海域と遮断する方法が取られています。岩手県田老町では,度重なる津波の被害を防ぐために昭和33年に延長135m、高さ10.65mの大防潮堤が造られました。
防災施設により被害の軽減は計れますが,人的被害をゼロにすることはできません。現在,わが国では,たいへん詳細な津波警報が提供されるようになっています。しかし,警報を受けて迅速な避難行動をとることの難しさが問題として残されています。 津波ワークショップ
▼スリランカ・コロンボ南で被災した列車
インド洋大津波の数値シミュレーション 津波の数値シミュレーションは,津波の高さや到達時刻の予測に有効な方法です。現在、インド洋大津波について観測結果と比較しながら,シミュレーションモデルの研究が進めています。 人工衛星がとらえた津波被災地 津波の直後から,人工衛星により被災地の状況把握が進められました。人工衛星の画像は,インド洋全域にわたる広大な地域の被害状況を把握する大きな手がかりとなったのです。津波で破壊された街 バンダ・アチェ 津波発生前と直後の衛星画像から,津波によりすべての建物が破壊され,橋や樹木も流されてしまったことが分かります。また,地盤沈下や津波による浸食によって海岸線の形も大きく変わってしまいました。 津波による広大な浸水域 スマトラ島 画像は,津波による浸水によって広大な地域が塩水により植生が死滅したため褐色になっているようすを捉えています。 |
||||||||||||||||


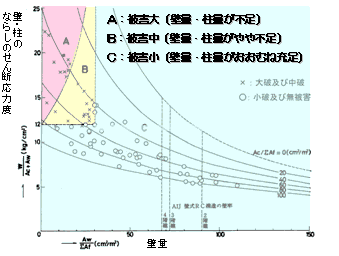

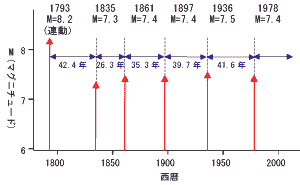
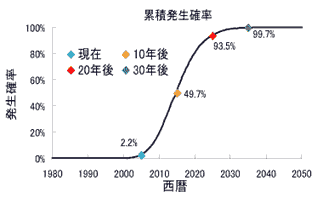
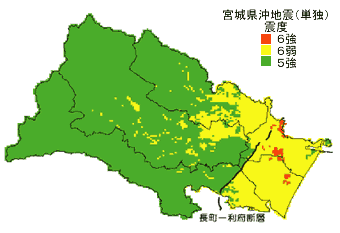
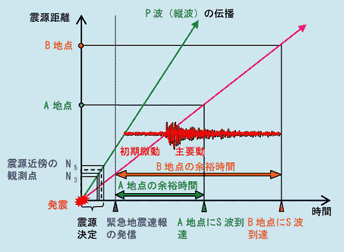


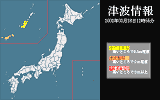 津波予報
津波予報
 平成16年12月26日に発生したスマトラ北西部沖地震(マグニチュード9.0)は約1000kmにも及ぶ震源域をもつ最大規模の地震でした。この地震により生じた津波は,インドネシア沿岸を襲い,その後タイ,マレーシア,インド東岸,スリランカに達し,死者・行方不明者は30万人を超える巨大災害を引き起こしました。
平成16年12月26日に発生したスマトラ北西部沖地震(マグニチュード9.0)は約1000kmにも及ぶ震源域をもつ最大規模の地震でした。この地震により生じた津波は,インドネシア沿岸を襲い,その後タイ,マレーシア,インド東岸,スリランカに達し,死者・行方不明者は30万人を超える巨大災害を引き起こしました。